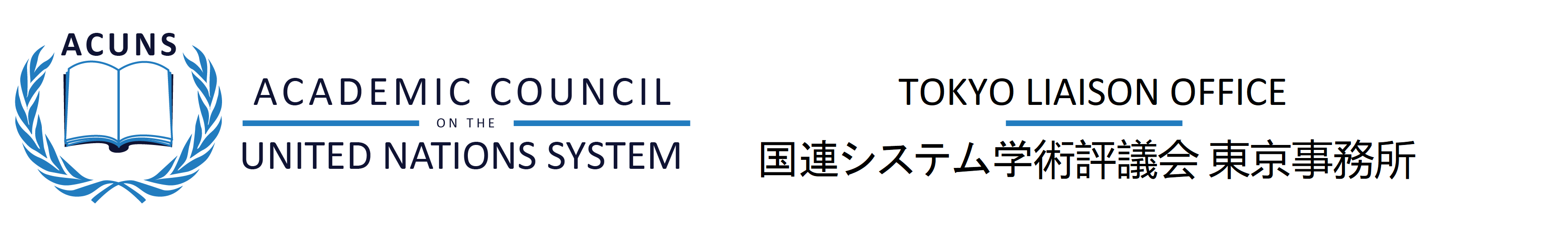京都国際平和構築センター(KPC)執行役員の範國将秀氏は、2025年度評議会において、センター創設の理念とこれまでの歩み、そして今後の展望について発言した。範國氏は、ACUNS(国連学術会議)との連携更新や大学理念「藝術立国」との関係、さらに国際的な教育環境の現状に言及し、京都芸術大学とKPCが目指す平和構築の方向性を明確に示した。
まず範國氏は、今年5月9日にACUNSとの連携協定を2028年まで更新したことを報告した。これは徳山理事長がウィーンを訪問し、ACUNS会長フランツ・バウマン氏との協議の上で締結されたものである。また、9月18日に行われた国連大学創立50周年記念式典には京都芸術大学の佐藤卓学長が出席し、今後もACUNSおよび国連大学との協働を一層強化していく方針を示した。
続いて範國氏は、KPCの理念に立ち返り、同センターが京都芸術大学の掲げる「芸術立国 ― 平和を希求する大学を目指して ―」の精神と重なり合うことを説明した。KPCは2021年3月に設立され、来年で5周年を迎える。「芸術と文化の力を通じて平和構築に貢献する」ことを目的とし、国際社会の課題である安全保障、開発、貧困、環境保全などに対し、知識と文化の共有を通じた貢献を目指していると述べた。
さらに、京都芸術大学が2027年に創立50周年を迎えることに触れ、「KPCの活動を通じて本学の理念をより多くの人々に伝えたい。皆様にもぜひ50周年記念事業に関わっていただきたい」と呼びかけた。
発言の後半では、京都芸術大学大学院の国際的な現状についても紹介した。現在、大学院生の約8割が中国人学生であり、入学倍率は5倍を超えるという。範國氏は、「優秀な日本人学生でも合格が難しいほどだが、これはむしろ誇るべきこと」と述べ、「中国人学生が将来、世界的なアーティストやデザイナーとして活躍し、その出身校が本学であるなら、それは非常に喜ばしいこと」と語った。
最後に、中国人学生が日本の芸術系大学院を志望する背景について、就職機会や日本文化の国際的影響力に触れ、「この潮流は現代の芸術教育の国際的魅力を象徴している」と結んだ。
評議会の詳細はこちらからご覧ください。
【発言全文(日本語)】
発言1
今年のトピックスとしては、まず5月9日にACUNSとの連携協定を2028年まで更新したことである。徳山理事長がウィーンにてフランツ・バウマン氏と協議の上で締結した。また、9月18日に行われた国連大学創立50周年式典には、佐藤卓・京都芸術大学新学長が出席した。今後もACUNSと国連大学との連携を一層強めていきたいと考えている。
京都国際平和構築センターは2021年3月に設立され、来年3月には5周年を迎える。本年はその節目の年でもある。さらに川口先生に新たにご加入いただいたことも踏まえ、改めて本学がなぜ京都国際平和構築センターを創設したのか、その理念に立ち返り述べたい。そして、本学の理念とKPC設立の重なる部分についても触れたい。
※読まれた「藝術立国 ― 平和を希求する大学を目指して ―」は以下のリンクからご覧いただける。
https://www.kyoto-art.ac.jp/info/philosophy/files/artsnation.pdf
京都国際平和構築センターは、この「芸術立国」の理念のもと、国際平和と文化、安全保障、開発と貧困、環境保全といった課題に対して、日本および国際社会における情報や知識を共有し、芸術・文化の活用を通じて国際社会の平和構築に貢献することを目的としている。
また、本学は2027年に創立50周年を迎える。来年度および2027年度は周年イヤーとなる。この後、中山教授からもお話があるが、ぜひ皆様には本学50周年に関わっていただきたい。ご協力をお願いするとともに、もしアイデアがあればぜひ本学に寄せていただければ幸いである。
発言2
触れていただいたので、本学のことを少しお話しさせていただく。本学大学院では、現在ほぼ8割が中国人学生である。競争倍率も非常に高く、5倍を超えており、日本人の優秀な学生でも合格できないほどである。現状では中国人学生の方がレベルが高い、という状況がある。
しかしながら、本学としてはこれについて全くネガティブな印象は抱いていない。むしろ美術、デザイン、建築といった分野において、中国人学生が世界的なアーティストやデザイナーとなり、その人物が本学の卒業生であるということになれば、それは非常に誇らしいことである。
このように、現代的な教育のあり方として非常に良い方向に進んでいると感じており、その点に関してストレスや負担を感じることは全くない。
発言3
それは報道でもよく取り上げられているが、現在、芸術系の日本の大学院は非常に多くの中国人学生の関心を集めている。その背景にはいくつかの理由がある。
ひとつは就職の問題である。デザイナーとしてのキャリア形成を見据え、日本の大学院で学ぶことに価値を見いだす学生が多い。もうひとつは、日本の漫画やアニメといったコンテンツが高い人気を誇っていることである。これが芸術系大学の魅力を高め、留学先としての需要を強くしている。
このように、中国人学生の増加は、現在の芸術系大学における一つの大きな潮流となっている。
(レポーター 井門孝紀)