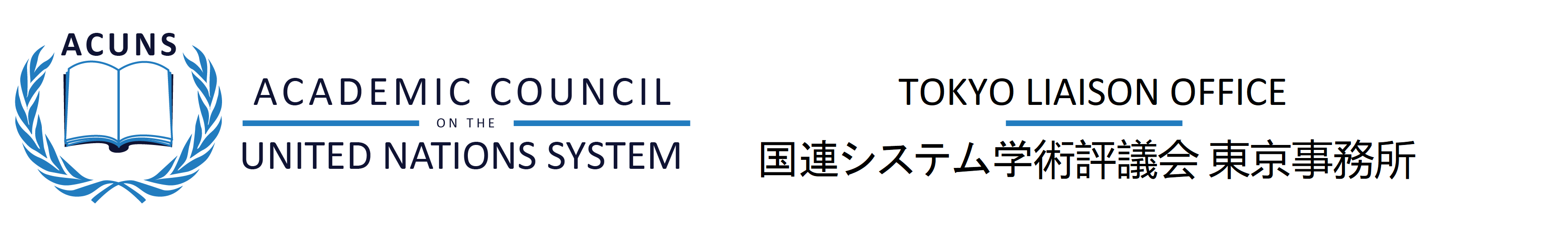2025年度京都国際平和構築センター評議会において、新たに評議員に就任した川口順子(かわぐちよりこ)元外務大臣が発言を行った。武蔵野大学国際総合研究所の名誉顧問でもある川口氏は、自身のこれまでの活動、世界情勢への見解、そして日本社会の課題について幅広く意見を述べた。
川口氏はまず、議員退任後の活動を振り返り、国際的な会議において日本の代表として発言してきた経験を語った。英語での議論を敬遠する傾向が日本の政治家に見られるなか、自らが国際社会における発言の場を担ってきたことを述べたうえで、「コロナを機に引退を決意し、現在はASEANと中国に関することのみを細々と続けている」と語った。そして、「明石先生からお話をいただいた時、内容を聞くまでもなく『イエス』と答えようと決めていた」と、新評議員としての就任に至る経緯を述べた。
続いて川口氏は、国際情勢に関する考察を示した。ドナルド・トランプ前米大統領の国連演説を例に挙げ、「かつてのアメリカが持っていた正義や民主主義の理念が失われている」と指摘。そのうえで、「トランプ後もアメリカは変わるのではなく、変わってしまった」と述べ、分断と格差の拡大が民主主義の危機を招いていると警鐘を鳴らした。さらに、「同様の矛盾は中国にも見られる」と語り、アメリカについては効率と公正、中国については自由と統制の相剋が二大国の内在的課題であると分析した。
また、国連改革についても言及し、「国連はすべてが機能していないわけではない。非伝統的安全保障、気候変動、SDGsなどの分野では大きな力を発揮している」と述べた。国連が持つ多様な影響力を積極的に社会に伝えることの重要性を強調した。
さらに川口氏は、ナショナリズムの台頭に伴う日本社会の変化にも触れ、「『日本人ファースト』を掲げる動きが国内でも見られる中で、なぜグローバル市民が必要なのかという問いに対して、明確な論理的整理が不可欠だ」と訴えた。そして、越境知の共有を進めるために日本が「一定のイシューについて中心的役割を発揮すべきだ」と強調した。最後に、「SNSに流されない抵抗力を持つ大人をどう育てるか」という現代社会の課題を提示し、参加者に問いかけた。
本発言は、国際社会における日本の立ち位置と、平和構築における知的基盤の形成に向けた示唆に満ちたものとなった。
(レポーター 井門孝紀)
発言の全文や、評議会の詳細はこちらからご覧ください。
【発言全文(日本語)】
発言1
何人かの方とはすでに名刺交換をさせていただいたが、ただいまご紹介いただいたように、私は武蔵野大学に設置されている国際総合研究所の名誉顧問を務めている。簡単に自己紹介をさせていただく。コロナ禍は私の生活を大きく変えた。議員退官後は国際的な場において、日本を代表して発言する機会が数多くあった。国際委員会や国際会議では英語で聴き、英語で発言するという役割を担ってきた。しかし日本の政治家は多忙で参加できない場合が多く、また時間のあるOBの方でも、会議が英語で行われるというだけで敬遠してしまう現状があった。そのため、私に出番が回ってくることが少なくなかった。コロナを機に引退を決意し、さまざまな仕事から身を引いた。現在はASEANに関することと、中国に関することの二つだけを細々と続けている。それ以外は全面的にリタイアしており、新たに勉強を重ねるエネルギーは残念ながらない。そんな折に、明石先生から評議員にならないかというお話をいただいた。私は外務大臣であった時代に明石先生に数多くのお願いをし、それを快くお引き受けいただいた経験がある。そのご恩もあり、内容を聞くまでもなく「イエス」と答えようと決めていたため、この度承諾させていただいた。
仕事内容の詳細についてはこれから皆様にご教示いただきたい。明確なイメージを持たずに参画しているため、ご迷惑をおかけするかもしれないが、どうぞよろしくお願いする。
発言2
先ほど明石さんがおっしゃったように、世界は混沌としていて、今後どういう方向に行くのかはわからない。ついこの間、トランプ大統領の演説が国連であったが、私も大体予期はしていた内容だったが、かつてのアメリカの考えかたや行動力など、自分の国益とともに正義、法の統治、民主主義などの国際社会を引っ張るアメリカの強みは片鱗もなかった。ただ、同時に、トランプがいなくなったあと、アメリカは変わるのかというと、専門家も言っているが、アメリカが変わったと考えるべきである。右派の政治活動家が暗殺されたニュースを見た方も多いと思うが、暗殺はいつの時代も問題だが、純粋な彼を信奉するアメリカ国民があれほど悲しむ事態になっているということ自体がアメリカの国民の分断を物語っている。私はアメリカには合計8年いたが、一番最初にアメリカに行ったのは16歳の時にアメリカの素晴らしい家庭で過ごし、アメリカが好きになった。あのアメリカをアメリカたらしめる考え方をベースにして育っているアメリカ人があのように行動している。競争社会がアメリカを強くしているのだが、その力を維持すること自体がアメリカの分断を招いている。効率性を第一に考える結果、経済が強いわけだが、それは強者が豊かになり、弱者が虐げられる社会であって、分配を重視しない結果。格差が広がっている。同じ種類の矛盾が中国にあるとも言える。国民をまとめている共産主義が経済の自由を阻害し、その矛盾が出現している。世界の二大国が制度に内在する矛盾を持っている。
もうひとつは、国連改革だが、私が気になるのが、国連は何もやっていないという言説である。国連は安全保障、平和を守ることに関しては機能していないのは事実なのであろう。しかし、すべてが機能していないとは言えない。国連が持っている力をしっかりと世界に広めることが大事なのではないか。環境大臣をしていた時には、国連の気候変動に関する影響力は素晴らしいと感じた。SDGsなどもそうである。それら非伝統的安全保障は国連の枠組みによって成り立っている。これは国連が持つ素晴らしい影響力の一例だがあまり語られない。条約等の規範を作ることや、国連総会では代表や総理、大統領が集まっ
て対面で話をする、このようなことを提供できることも国連の強みだ。このような側面をしっかりとみなさんに伝えていくことが大事であると考える。
発言3
アメリカや他の国で起こり始めている動き、さらにはマレーシアの事例にも触れられたように、ナショナルとインターナショナルの問題はもはや「対岸の火事」ではなくなっている。日本でも「日本人ファースト」を掲げて選挙で支持を集める政党があり、神谷氏の演説会場が熱狂的な雰囲気であると聞く。また、「我々が納めている税金をなぜ留学生に使うのか」という意見も増えてきている。その中で、なぜグローバル市民が必要なのか、ナショナルな市民を育てることと矛盾するのかどうかーーこの目的について論理的な整理が不可欠であると感じる。それがなければ、全体が国内志向に傾く中で国際的な取り組みはますます困難になるだろう。越境知の問題についても、大学に限らず広く社会全体に広げる必要がある。ネットを活用することは一つの方法だが、日本が谷間に落ちるのではないかと危惧している。例えば、イギリスの『エコノミスト』のようにリアルタイムで国際的な討論番組が行われても、日本では時差の関係で深夜にあたり、結局参加しない。アメリカ東部と日本は時間が反対であるため、どうしても日本がリーダーシップを発揮しにくい。この問題の解決のためには、日本が一定のイシューについて中心的力を発揮することだと思う。
最後に質問をさせていただきたい。知のプラットフォームを構築する上で、SNSに流されない、抵抗力を持つ大人 をどのように育てるのかという点である。これは現代社会において極めて大きな課題であり、どのような言説や議論があるのかを伺いたい。