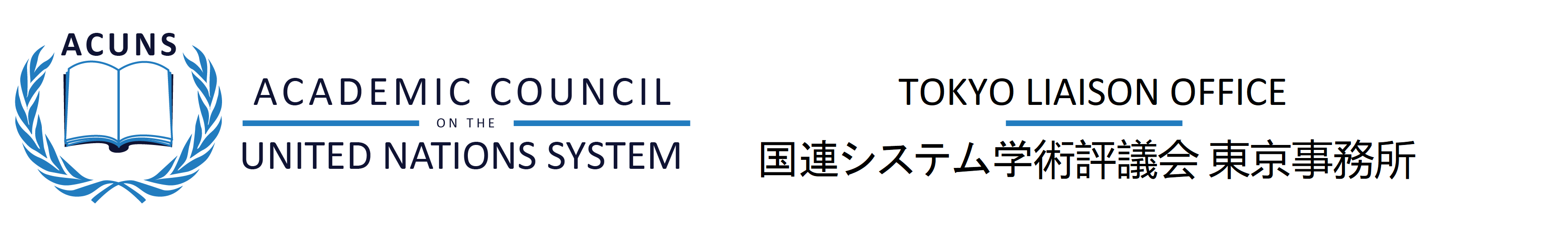京都国際平和構築センターの評議会において、同センター評議員であり日本ユネスコ協会連盟理事長の鈴木佑司氏が、杉村美紀上智大学学長の基調講演を受け、教育の国際化と「越境する智(ち)」の可能性について見解を述べた。
鈴木氏はまず、杉村学長の講演を「非常に説得力があり、アジア地域を中心とした高等教育の未来を明確に示すものだった」と評価した上で、長谷川祐弘名誉会長の説明に関連し、「地政学的境界を越え、国家の枠を超えて“智”のプラットフォームを築くことは本当に可能なのか」と問題提起した。
東南アジア研究を専門とする立場から、鈴木氏は「国家が経済成長を遂げるほど、教育を国家の支配装置として取り込み、格差を固定化する傾向が強まる」と指摘。多民族・多宗教国家が多い東南アジアでは、権力が教育を独占することで、社会的排除の構造が生まれていると警鐘を鳴らした。その上で、「そもそも国家はなぜ建設され、国民形成は何のために行われたのか」という根本的な問いを改めて投げかけた。
一方で、アジアにおいては「智が国境を越える動き」が確実に進展していると評価した。コロナ禍を契機にオンライン環境が整備されたことで、国境を越えた新たな学術交流が広がっているが、各国の政治的思惑によって学問の自由が阻まれる現実もあるという。「若い研究者が自由に研究できず、不当な拘束を受ける危険すらある」と憂慮を示した。
さらに自身の大学の事例を挙げ、「教員1500人のうち100人以上が中国人研究者であり、今後はネパールやベトナムからも受け入れる予定だが、政府間関係が必ずしも良好ではない中で、こうした国際連携をどう維持・発展させるかが大きな課題だ」と語った。
続けて鈴木氏は、「ユネスコなどの国際機関が高等教育の国際化を牽引する一方で、初等・中等教育で排除された人々に学びの機会をどう確保するかが問われている」と指摘。各国が大学ランキングの上昇や論文数の増加など国際競争力強化に資金を投入する一方で、基礎教育が軽視されるという「歪み」を問題視した。
また、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)が実際には新たな排除を生み出す矛盾や、国語教育が優先されることで多言語教育が後退する傾向にも触れ、「大学の国際化が進む一方で、基礎教育が取り残される危険がある」と警鐘を鳴らした。
最後に鈴木氏は、「国際化と基礎教育をいかに両立させるか」という問いを提示し、持続的な教育のあり方を模索する重要性を訴えた。
評議会の詳しい内容は、こちらからご覧いただけます。
(レポーター 井門孝紀)
発言原文
鈴木佑司 京都国際平和構築センター評議員 日本ユネスコ協会連盟理事長
杉村先生、ありがとうございました。非常に説得力のあるご講義であり、高等教育、特にアジア地域を中心とした未来への方向性を明確に示していただいた。
長谷川先生がご説明されたポイントについて、質問をさせていただきたい。地政学的な境界というよりも、国家を超えて「智(ち)」のプラットフォームを築くことが果たして可能なのか、という点である。私のように東南アジアを研究対象とする者から見れば、国家が経済成長を遂げるにつれて教育を国家内部に取り込み、支配の道具としてしまう傾向が強まる。その一方で、東南アジアの国家は多様な宗教、文化、人種を内包しており、多民族・多宗教国家であるがゆえに、権力が教育を独占し、教育格差が構造化されてしまう。この状況を見ると、そもそも国家はなぜ建設され、国民形成は何のために行われたのか、という根本的な問いが浮かび上がる。
学者の間では、アジアにおいて「智が国境を越える動き」が確かに進んでいると考えられている。これはこれまで私が見たことのないような新しい学術交流であり、特にコロナ禍を経てインターネットの普及によって国境が曖昧になった結果でもある。高等教育における国際協力は非常に強まっているが、各国の権力にとって不都合であれば阻まれてしまう。若い研究者は自由に研究できないどころか、不当な理由で拘束される危険すらある。
実際、私の大学には1500人の教員のうち100人以上が中国人研究者である。これからはネパールやベトナムからの研究者も迎える予定だが、それらの国々と政府関係が必ずしも良好ではない。そのような状況をどう突破していくのか、大きな課題である。
さらに申し上げたいのは、ユネスコなどの国際機関が華やかな高等教育の国際交流を担う一方で、各国で取り残されている人々、すなわち初等・中等教育の段階で排除されてしまった人々に教育の機会をいかに与えるかという課題である。国家は国際競争力を高めるために、大学のランクを上げることには多額の資金を投入し、外国人研究者を招聘して論文数を増やし、国際的評価を高めようとする。しかし、その足元で国民に対する基礎教育が軽視され、排除のメカニズムが働き、多数派が教育を独占するという歪んだ現象が生じている。
私の経験でも、特定の人々に優先的に大学ポストを与えるという「アファーマティブ・アクション」のような仕組みが、かえって排除を助長していた。また、国語教育が優先され、多言語教育が後退する傾向も見られる。こうした現実を見ると、大学の国際化が進む一方で基礎教育が疎かになってしまう危険がある。
この点を踏まえて、どのようにすれば国際化と基礎教育の両立を図れるのか、その方策について教えていただきたい。